
よく「亜鉛を摂取すると良い」と聞くことはないでしょうか。
筆者も上司に免疫力が付くからと、亜鉛を勧められたことがあります。
よくサプリメントでも見かける亜鉛ですが、実際には
- 十分に摂取すると、どんなメリットがあるのか
- 不足すると、どんな症状になりやすいのか
などさまざまな疑問点が浮かび上がってきます。
そこで今回は、亜鉛を摂取することでのメリットや、不足した場合、体にどんな影響を及ぼすのかなど、徹底解説していきます。
また、亜鉛を多く含む食品なども記載してますので、最後までお付き合いいただければと思います。
亜鉛とは
亜鉛とは、人間が活動するために必要な代謝の過程で働く、酵素の構成成分として必要不可欠なミネラルです。
亜鉛は人間の体内に約2gあり、血液や皮膚に多く存在します。その他にも、骨や腎臓、肝臓、脳、髪の毛など新陳代謝の盛んな細胞に多く存在し、新陳代謝を助けているのです。
また、ミネラルの中でも不足しがちな栄養素であるため、意識して摂取する必要があります。
亜鉛の役割

亜鉛は、人間が活動するために必要不可欠なミネラルですが、実際どのような役割を果たしているのでしょうか。主にメリットは以下になります。
- 味覚を正常に保つ
- 抗酸化作用
- 免疫力の向上
- 成長・発育
- 髪や肌の健康維持
- 生殖機能の改善
- うつ病の改善
なんとなく必要だからと摂取しているよりも、どのような役割か理解して摂取しているほうが、より効果を感じられると思うので、この機会に知っておきましょう。
味覚を正常に保つ
舌にある味蕾(みらい)という受容器官で、私たちは味を感じ取ります。
亜鉛はこの味蕾の中の味細胞において、重要な働きをしているのです。
味細胞は短期間で細胞を次々に生まれ変わらせているため、材料となる亜鉛を常に必要としています。
亜鉛をしっかりと摂取することで、味蕾の働きを正常に保つことができ、食事を美味しく食べることができるのです。
抗酸化作用
亜鉛は体内のビタミンAの代謝を促します。
ビタミンAの抗酸化作用の活性化を促し、過酸化脂質の害を防ぐことで、アンチエイジング・生活習慣予防にも効果が期待できるでしょう。
免疫力の向上
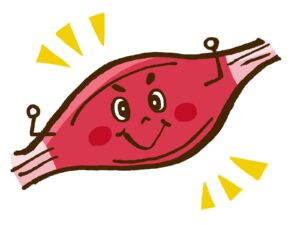
亜鉛が十分に体内にあると、風邪や感染症にかかりにくくなるのをご存知でしょうか?
粘膜を保護するビタミンAを体内に止める効果があり、のどの痛みや鼻水、鼻詰まりなどの症状を緩和してくれます。
病気を引き起こす細菌を攻撃する白血球にも亜鉛が含まれているので、傷や病気の早期回復にも亜鉛は役割を発揮するでしょう。
成長・発育
タンパク質と合わせて亜鉛を摂取することで、全身の新陳代謝がより活性化されます。
新陳代謝が活発な時期に亜鉛はより必要になるので、特に成長期のこどもには過不足なく、亜鉛を摂取することが必要です。
髪や肌の健康維持
髪の毛や皮膚もタンパク質からできているのをご存知でしょうか?
亜鉛を摂取することで、タンパク質の代謝を促し、髪や皮膚のトラブルを改善します。
タンパク質を摂れば髪や皮膚が丈夫になるということですね。
髪や皮膚も新陳代謝が早いペースで行われるため、亜鉛を積極的にとることで美肌・美髪効果につながります。
髪や皮膚のために亜鉛が大切ということがご理解いただけたでしょう。
生殖機能の改善
男性の前立腺や精子に亜鉛は多く存在し、精子の形成に必要とされ、生殖機能に役立ちます。
うつ病の改善
感情のコントロールや、記憶力を保つには神経伝達物資流が正常に作られ、働く必要があります。
うつ状態は脳の機能が低下し、神経細胞の刺激伝達がスムーズにいかないためと考えられていますが、この神経伝達物質を作るのに必要なのが亜鉛です。
亜鉛が体内に十分にあることで、精神安定や脳の機能を高め、うつ状態緩和に効果があると考えられています。
亜鉛不足で起こりやすい症状

亜鉛は体内で蓄えることができないため、忙しい現代社会では不足しがちな栄養素でもあります。
亜鉛が不足すると一体どんな症状が起こるのでしょうか。
よくある症状をご紹介致します。
肌荒れや皮膚炎
皮膚のタンパク質合成に関わる亜鉛が不足すると、肌荒れや皮膚炎を引き起こします。
なぜなら、皮膚が新しい細胞に生まれ変わるターンオーバーが上手くいかなくなり、傷の治りが遅くなり、跡も残りやすくなってしまうためです。
タンパク質の合成に関わる亜鉛が不足すると、肌荒れだけでなく口内炎や爪が割れる・変形するなど、体のさまざまな場所で炎症を起こします。
これらの炎症を抑えるには、活性化酸素除去酵素が必要です。
それを構成する亜鉛が不足すると、炎症が抑えきれなくなってしまいます。
なので、亜鉛を日頃から摂取するようにしましょう。
抜け毛増加や薄毛
髪の毛の約90%以上はタンパク質から作られています。
そして、タンパク質はアミノ酸から構成されていますが、髪を作っているケラチンはシスチンを中心とした18種類のアミノ酸から作られます。
このシスチンは食事で摂取するしかない、必須アミノ酸のひとつであるメチニオンから合成されます。
しかし、アミノ酸は単独で生成を行うことはできず、亜鉛の助けを必要とするため、亜鉛が不足すれば、アミノ酸が体内にあってもケラチンを合成することができないのです。
味覚障害
味覚を感じるのは、舌表面に多くある味蕾という小さな器官です。
味蕾の中には味細胞という味覚センサーがあり、この味細胞は新陳代謝がはやく、約1ヶ月毎に生まれ変わっていきます。
この味細胞の再生には亜鉛が必須なのですが、亜鉛は体内で合成、蓄えたりできません。
なので、食事やサプリメントで摂取をしていきましょう。
食欲不振
亜鉛が不足すると、胃や腸などの消化管の働きが悪くなり、食欲が低下します。
食べる量が減るため、亜鉛がさらに足りなくなり、悪循環を招いてしまうのです。
貧血
亜鉛は赤血球を作るはたらきに関係しているため、亜鉛不足の人は貧血になることがあります。
免疫力低下

亜鉛が不足すると、免疫機能が低下するため、ウイルス細菌に感染しやすくなります。
また、感染に対する抵抗力も弱くなり、重症化したり、症状が長引くなどの症状が出やすくなるので気をつけましょう。
亜鉛の食事摂取基準
下記の表は健康長寿ネットを参考に作成いたしました。
亜鉛の食事摂取基準量 男性(mg/日)
| 年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 耐容上限量 |
| 10歳〜11歳 | 6 | 7 | ー |
| 12歳〜14歳 | 9 | 10 | ー |
| 15歳〜17歳 | 10 | 12 | ー |
| 18歳〜29歳 | 9 | 11 | 40 |
| 30歳〜49歳 | 9 | 11 | 45 |
| 50歳〜64歳 | 9 | 11 | 45 |
| 65歳〜74歳 | 9 | 11 | 40 |
| 75歳以上 | 9 | 10 | 40 |
亜鉛の食事摂取基準量 女性(mg/日)
| 年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 耐容上限量 |
| 10歳〜11歳 | 5 | 6 | ー |
| 12歳〜14歳 | 7 | 8 | ー |
| 15歳〜17歳 | 7 | 8 | ー |
| 18歳〜29歳 | 7 | 8 | 35 |
| 30歳〜49歳 | 7 | 8 | 35 |
| 50歳〜64歳 | 7 | 8 | 35 |
| 65歳〜74歳 | 7 | 8 | 35 |
| 75歳以上 | 6 | 8 | 30 |
| 妊婦(付加量) | +1 | +2 | ー |
| 授乳婦(付加量) | +3 | +4 | ー |
- 推定平均必要量:半数の人が必要量を満たす量
- 推奨量:ほとんどの人が必要量を満たす量
- 耐容上限量:過剰摂取による健康障害を未然に防ぐ量
上記、表を見てみると、男性の場合18歳〜74歳の1日の摂取量は11mgで、75歳以上は10mg、女性の場合、18歳以上は8mgです。
また、耐容上限量を超え、亜鉛を過剰摂取した場合、銅欠乏、貧血、胃の不調など、さまざまな健康被害が生じることが知られているため、男性であれば18歳〜29歳までは40mg、30歳〜64歳までが45mg、65歳以上も40mg、女性であれば、18歳〜74歳で35mg、75歳以上で30mgと設定がされています。
ちなみに、通常の食事による、亜鉛の過剰摂取の可能性は低いと言われていますのでご安心ください。

取り過ぎも良くないんですね!
亜鉛を多く含む食品

亜鉛は健康維持に必要不可欠な栄養素ですが、あらかじめ含有量が多い食べ物をチェックし、効率よく亜鉛を摂取しましょう。
| 魚介類 | 生牡蠣|13.2mg
煮干し|7.2mg たらこ|3.1mg しらす干し|3.0mg かつお節|2.8mg ほたて|2.7mg うなぎの蒲焼き|2.7mg |
| 海藻類 | 焼きのり|3.6mg
カットわかめ|2.8mg あおさ|1.2mg きざみ昆布|1.1mg ひじき|1.0mg |
| 肉類 | 豚レバー|.6.9mg
牛肩ロース|5.6mg 牛もも肉|4.8mg 牛リブロース|4.5mg 鶏レバー|3.3mg 豚肩ロース|3.2mg 豚肩肉|3.1mg 鶏もも肉|1.6mg |
| 卵・乳製品 | プロセスチーズ|3.2mg
全卵|1.3mg 牛乳|0.4mg |
| 豆類 | きな粉|4.1mg
油揚げ|2.5mg 納豆|1.9mg 枝豆|1.4mg こしあん|1.1mg 木綿豆腐|0.6mg |
| 穀類 | 静白米・・・0.6mg
そば・・・0.4mg |
| ナッツ | カシューナッツ|5.4mg
アーモンド|4.4mg |
| 野菜類 | 切り干し大根|2.1mg
しそ|1.3mg たけのこ|1.3mg ごぼう|0.8mg |
亜鉛は肉類や魚類に多く含まれます。
生牡蠣などかなり豊富に含まれておりますが、日常的に食べる機会が少ないため、ナッツ類など手軽に食べられるものから、はじめてみるのがおすすめです。
亜鉛はアルコールの摂取で消費されてしまう
お酒を飲むと、アルコールを分解する酵素の活性化に亜鉛を大量に消費することと、亜鉛を体外に排出する2つの作用があるので、注意が必要です。
亜鉛はビタミンCと一緒に摂取して吸収効率を上げる
亜鉛はビタミンCとクエン酸と一緒に摂取することで、吸収効率を上げることができます。
クエン酸には亜鉛のミネラルを包み込み、体への吸収を助ける作用があり、ビタミンCにはそのクエン酸の働きを助ける効果があるので、たとえば、生牡蠣にレモンを垂らすなど、ひと工夫して吸収効率を高めてみましょう。
サプリメントの摂取も手軽でおすすめ
理想は食事から摂取したいですが、毎日意識して亜鉛を摂取するのは難しいでしょう。
そんな方には、サプリメントの摂取が手軽でおすすめです。
基本的に3食バランスの良い食事を摂り、プラスしてサプリメントを摂取するという形ですが、飲んだからといってすぐに効果が出るものではないので、継続して飲みましょう。
筆者は、夜寝る前に飲んでます。
また、一度にたくさん飲んだからといって、効果がある訳でもないので、目安量はきっちり守りましょう。
まとめ

いかがでしたでしょうか?
亜鉛を十分に摂取できていると、私たちが健康で豊かに暮らしていけるのが、分かったかと思います。
逆に亜鉛が体内に不足していると、風邪や感染症にかかりやすくなったりなど、影響は大きいです。
ですが、食事で摂取ができなくても、サプリメントなどで手軽に摂取できる時代になっているのも確かです。
現代はストレス社会とも言われ、5人に1人はうつ病にかかっていると言われています。
亜鉛にはうつ病改善の効果もありますので、1つしかない自分の体を大事にし、毎日健康でいてくだされば幸いです。
少しでも参考になればと思います。

コメント